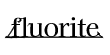若干の桃色要素あり。
「どうした? 浮かない顔して」
俺の恋人――ディアッカが笑いながらカフェラテを差し出す。
疲れた時に甘いものが欲しいと思う俺のことを、ディアッカは随分よく見ている。
どうしてコイツはこう、気がつくというか、人たらしなのか――。
悔しいながらに、そう感じた。
「疲れた。目が限界だ」
そう言って、カフェラテを手に取った。
「まだ仕事残ってんのか? あんま、根詰めるなよ」
ディアッカは、ソファで端末のキーボードを叩く俺の横に腰を下ろして、頬にキスをした。
「おいディアッカ……」
「いーじゃん。カフェラテ淹れたご褒美、頂戴?」
ここぞとばかりに俺の腰を抱く。
ディアッカはどうやら、最近家でも仕事ばかりの俺が面白くないようだ。
面白くないと言っても、同じ仕事をしているのだから、背に腹がかえられぬ事情があることくらい、痛いほど分かっているはずなのだが。
俺にはどうも、こういうコイツの拗ねるところが分からない。まぁ――理解する気もないのだが。
「俺、お前の好きなものたくさん作ってあるぜ? ビーフシチュー、ラグーソースのパスタ、海老のサラダ、えーとそれと……」
「はぁ!? そんなに大量にか!?」
二人分なのに、そんなに作るなんて……。
俺はいつも、コイツが本当は出来るくせに爪を隠しているのか、それとも本当の馬鹿なのか判断に迷う。いや、本当の馬鹿野郎なのだと、薄々気付いてはいるのだが。
「いくらなんでも太るとか思ってるだろ? 俺はいーぜ。イザークが太ってても、ゴツくてマッチョでも」
てか、どんな見た目でも、イザークは可愛いし。
コイツに憧れる女なら顔が真っ赤になってしまうようなことを、さらりと言ってのける。
「ディアッカ……」
俺は自慢げな顔のディアッカを見て、ため息を吐いた。
「あ、あとさ、日本食。寿司も好きだよな。それは俺流石に作れなかったけど、今度とびきりうまいのを食べような」
「あ……寿司か……」
幼い頃、ディアッカの家で初めて口にした、生魚の載った寿司。
食べたいが、大変な贅沢品な上に、プラントでは寿司を作れる日本食シェフが限られている。
「今度、シェフをブッキングしとくからさ」
全くもって、ディアッカは俺に甘いのだ。
「お前、サービス精神が旺盛すぎやしないか。その精神力をもっと仕事に充てたらどうだ」
端末の画面に向き直り、俺はカフェラテを啜った。
美味い。
「なー、美味い?」
腰には手を回し、肩には頭を載せ、これ以上ないほど密着してディアッカは俺に尋ねた。
「あぁもう、鬱陶しいっ!! 離れてろっ!」
一喝すると、ひょいっと端末を取り上げられた。
そして呆気なくカフェラテのマグカップも取り上げられて、ソファの座面に押し倒されてしまった。
「ハイ、今日はおしまい」
「はぁあ!?」
「俺が今、決めマシタ」
ニコニコ笑ってそう言うと、反論しようとした俺の口をすかさず唇で塞いだ。
「んッ――!」
素肌に着た白いオックスフォードシャツをスラックスから引き出され、腹に温かい手のひらが這わされる。
「あっ……」
思いがけない接触に思わず声が漏れた。
「可愛い……」
ディアッカはなお、胸の方に向かって柔らかくなぞる様に手を進めた。
「まだ、仕事がっ……」
「大丈夫。シてくれたら、有能な俺が全部後で片付けますから」
お前が気絶しちゃった後で。
と、聞き捨てならないセリフも吐いた。
「イザークが、俺じゃなきゃだめになるように、ちゃんと教育しなきゃね……」
ニヤッと笑って言った気がしたが、俺はディアッカの手がもたらす快感に着いていくので精一杯で、反論することも出来なかった。
end.