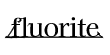※ガンカフェZ.A.F.T.ディナーストーリー前提DY小説
プラントの首都、アプリリウスの第一基であるアプリリウス・ワンの中央シャフト周辺、高層住宅の摩天楼の中の一角に、彼らの住む家はあった。
声紋による個人識別を行う地下駐車場を、白いスポーツタイプの自家用エレカで滑り降りたイザーク・ジュールは、コンクリートに刻まれた仕切り通りにエレカを収める。
エンジンを切り、静寂の支配する車内で深いため息を吐くと、白い軍服の首もとをやれやれと緩めた。
久しぶりに会ったアイツは、思いがけず元気そうで、懐かしくて、そして――。
イザークが「その人」に想いを馳せようとしたところで、妨害するように携帯端末の着信音が鳴った。
軽く画面に目を遣ると、そこには「Dearka Elthman」、そしてその名の後にはテキストメッセージが示されていた。
エレカが敷地に入った連絡が彼の端末に届いたのだろうと思い至り、家で首を長くして待っているのであろうその通知の主を思う。
にわかにイザークは助手席に放り投げたアタッシェケースを掴み、エレベーターへと急いだ。
***
「お、お疲れー。遅かったな」
「長引いたんだ。悪いな」
イザークが廊下を抜けてリビングダイニングへ入ると、ディアッカがソファから立ち上がった。
珍しいこともあるもんだよな、とディアッカ・エルスマンは言いながら、キッチンへ入り、冷えたミネラルウォーターのボトルをイザークに差し出した。
キッチンカウンターのハイチェアに腰掛けたイザークは、軍服のジャケットを背もたれに掛けてそのボトルを受け取った。
「で、どーだった? 見込みのあるやつ、居た?」
「ま、単なる広報のようなモノだ。期待はしていなかったが、見込みのありそうなのも居た」
「いいじゃんか。リクルーティングねぇ……お前がそんなことするようになるなんて、俺たちオッさんになったのかねぇ」
「うるさい。――それにアイツも、まぁ元気にやっているようだった」
「そうか」
アイツ――。ふたりの同期であり、僚友であり、一度は離れ、そして戻った、英雄アスラン・ザラ。
ザフト内部でも、伝説ではあれ賛否の分かれるかの人物を、イザークは口ではあれこれ述べながらも、それでも好ましく受け止めていた。
イザークが自身の背中を預けられる数少ない人物の内のひとり――。
イザークとディアッカにとって、過ぎ去って二度と戻らない懐かしいあの日の絆そのものだった。
「議長もニクイことするよな。イザークとアスランで広報しようってんなら分かるけど? 緑の俺まで引っ張り出して――それにニコルも。あんな芸能人じみたプロモーションビデオまで作ってさ。俺、まさか赤服をコスプレで着ることがあるとは思ってなかったぜ」
ディアッカは過日、議長たっての依頼とのことでアーモリー・ワンに出向くことになった。
何事かとおっかなびっくりしていたら、用意されていたのは巨大な撮影スタジオに真新しい赤服、そしてヘアメイクと大勢のエキストラたちだったのだ。
モデルになろう、とは露ほども考えたことがないディアッカだったが、その「仕事」は軍人の仕事には凡そ思えぬ、「モデル」の仕事そのものだった。
思っていることが顔に出にくいディアッカだったが、懐かしい赤服を着て勇ましいポーズを取り、フラッシュが瞬いた時には、流石に一瞬引き攣った表情をしてしまったような気もしていた。
「で? ――お前も、着たの。アレ」
「アレとはなんのことだか知らんが、久しぶりに赤に袖を通した」
「うわ、やっぱり」
――その写真、どっかに載るよな。載らないはずない、次のザフト広報誌とか?
沸き立つディアッカに呆れた声でイザークは答えた。
「テレビCM、広報誌、ニュース、一通り掲載があるそうだ。まったく、大規模な新兵募集といったところか?」
「いやー、俺はともかく、議長やるじゃん。お前の赤服姿、また見ることになるとはねぇ」
「気色悪い顔をするんじゃない!」
思わず口元のゆるんだディアッカを一喝すると、イザークはボトルの水を一気に飲み干した。
「戦う仲間が増えることは嬉しいさ。――孤独よりは余程な」
「イザーク……」
イザークは、幾分抑えた声でポツリと漏らした。ディアッカは、憂いありげに伏せられた彼の目を見た。
「アスランも――、アスランも、俺の隊に来ればいいんだ。こき使ってやるさ」
ややあって、イザークは決意したように空のボトルを乱暴にカウンタートップに叩きつけると、徐に立ち上がった。
「俺みたいにね」
「そうだ」
「お疲れさん」
「あぁ、そうだ――俺はまだ持ち帰ってきた仕事があるから、部屋はしばらく開けないでくれ」
「またか? いいけど」
無理すんなよ、と、ディアッカは銀に光る無機質なアタッシェケースを見て言った。
近頃は、イザークがディアッカに詳細を伝えずに行う仕事も多いようだ。恐らくは、議長絡みの――センシティブな内容なのであろうと、ディアッカは踏んでいた。
(とんでもないジョーカーでなければいいけどな)
どこか人を信用し切らないところのあるディアッカは、主人への忠義に厚いイザークの乗る船が、せめて泥でできていないことを願っていた。
イザークの目元には、うっすらと撮影用メイクで隠されているものの、寝不足でできた隈が刻まれていることをディアッカは知っていた。
「先、寝てる」
「あぁ」
イザークは自身の書斎に消えていく。その瞬間、イザークが端末の着信を受け、彼らしくもない疲れて険しい表情をしたことを、ディアッカは見逃さなかった。
(俺は必ず、お前のそばにいる)
「救世主」が、大きな鎌を携えた死神でないことを願い、ディアッカは彼だけの「主人」への忠誠を誓う。
(ヒトの心は自由、だからな)
ディアッカは嘯き、この部屋の主人のジャケットをクローゼットに仕舞い込んだ。
end.